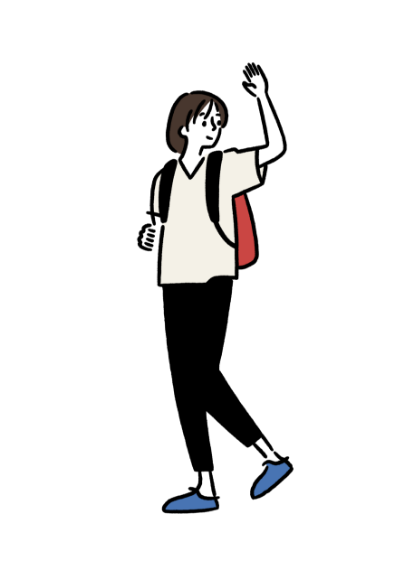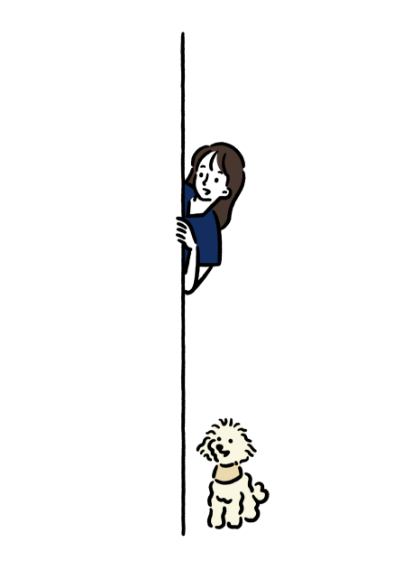【中秋の名月】

中秋の名月は、旧暦8月15日の夜に見られる満月のことを指します
日本ではこの時期に月を愛でる「お月見」の風習があり、秋の収穫を祝い、月への感謝を捧げる伝統的な行事です
《中秋の名月の特徴と風習》
中秋の名月は中国の唐代から伝わり、平安時代に日本に広まりました。貴族が月を眺めながら詩歌を詠んだり、宴を楽しんだりしたのが始まりです
農耕文化では、秋の収穫を祝い、月を神聖な存在として感謝する意味合いも強いです
お供物としては月見団子が有名で。丸い団子を満月に見立てて供えます
白い団子をピラミッド状に積むのが一般的で、地域によってはあんこ入りのものや、色付きのものもあります。米粉で作られ、素朴な甘さが特徴です
ススキは月の神様の依り代とされ、稲穂の代わりに飾られます。魔除けの意味もあるとされます
季節の野菜や果物、サトイモ(里芋)、栗、柿、豆などが供えられることも多いです
これらは秋の収穫を象徴します
月を愛でながら日本酒を飲む習慣もあり、特に「月見酒」と呼ばれます
《食べ物》
〈月見団子〉
前述の通り、メインのお供え物であり、食べることで月への感謝を表現します
シンプルな白玉団子に、きな粉や黒蜜をかけたり、地域によってはゆでた里芋と一緒に食べることも
〈里芋料理〉
里芋は「芋名月」とも呼ばれる中秋の名月にちなみ、煮物や汁物で楽しまれます
〈栗ご飯や松茸料理〉
秋の味覚として、栗や松茸を使った料理もお月見の食卓に並ぶことがあります
〈月見バーガー〉
現代では、ファストフード店(マクドナルドなど)で中秋の名月にちなんだ「月見バーガー」が季節限定で販売されるなど、伝統と現代文化が融合しています
〈飾り付けと楽しみ方〉
・ススキや団子を窓辺や縁側に飾り、月を眺めながら家族や友人と過ごすのが一般的
・地域によっては、子供たちがお月見の夜に「月見泥棒」と呼ばれる風習で、供えられた団子や果物を「盗む」遊びもあります
これは豊作を願うユーモラスな習慣です
《文化的背景》
・中秋の名月は、単なる満月の夜ではなく、自然への敬意や季節の移ろいを愛でる日本の美意識が反映されています
・現代では、都市部でもベランダでお月見を楽しんだり、SNSで月を撮影してシェアするなど、新しい形で親しまれています
という事で治療院では中秋の名月には月見団子をいただきました。