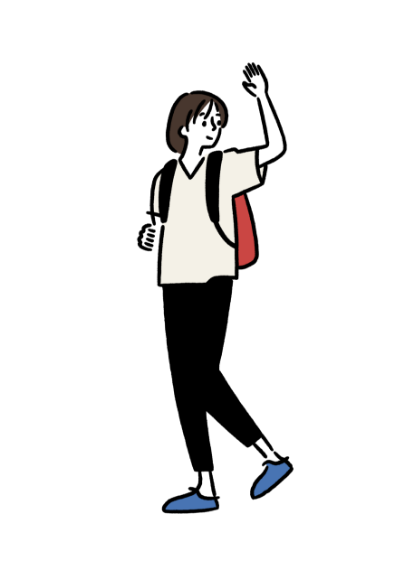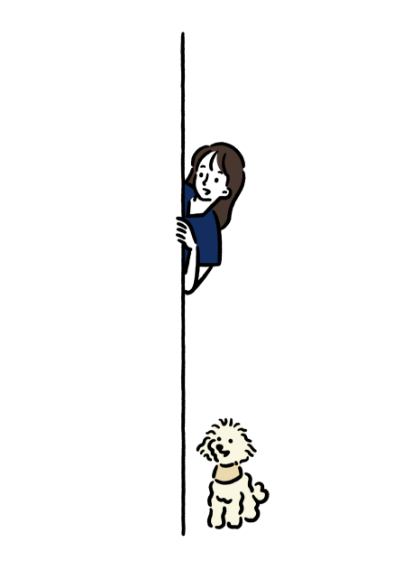【寒露】

寒露は、二十四節気の1つで、通常10月8日または10月9日に訪れます。2025年は10月8日です
この時期は秋が深まり、朝晩の冷え込みが強くなり、露が冷たく感じられることから「寒露」と呼ばれます
暦の計算に基づき、太陽の黄経が195度に達する日であり、気候的には秋の清涼な空気と収穫の時期を象徴します
《寒露の特徴》
夏の暑さが和らぎ、秋らしい涼しさが増す時期。朝露が冷たく感じられ、紅葉が始まる地域も多いです
秋の虫の声が響き、渡り鳥が姿を見せ始めます。農作物は収穫のピークを迎えます。
日本では、古くから農業や自然と密接に関わる節気として意識され、季節の変わり目を大切にする風習があります
《寒露に関連する食べ物》
寒露の時期は秋の食材が豊富で、旬の食材を使った料理が楽しめます。以下は寒露におすすめの食べ物や食材です
《秋の味覚》
〈サンマ〉
秋の代表的な魚。脂がのったサンマの塩焼きは、寒露の時期に特に美味
〈栗〉
栗ご飯や栗の甘露煮など、ほっくりとした甘みが秋の食卓を彩ります
《きのこ〉
しいたけ、しめじ、舞茸などを使った鍋や炊き込みご飯が季節感を演出
〈サツマイモ〉
焼き芋やスイートポテトなど、甘みが増す秋の定番
〈柿〉
甘柿や渋柿を使ったデザートやサラダがおすすめ。
《収穫祭の料理》
寒露は収穫の時期と重なるため、新米を使ったおにぎりや炊き込みご飯が食卓に並びます
地域によっては、収穫を祝う行事で五穀豊穣を祈る料理(赤飯やお団子)も
朝晩の冷え込みに対応し、根菜や豆類を使った味噌汁や鍋料理が体を温めます
里芋やごぼう、かぼちゃを使った煮物やスープ
《寒露の食文化と風習》
日本では「旬」の食材を大切にする文化があり、寒露の時期は秋の恵みを活かしたシンプルな料理が好まれます
一部の地域では、収穫感謝の祭りや秋祭りが行われ、地元の食材を使った料理が振る舞われることも
健康への配慮: 冷え込む時期なので、身体を温める食材(生姜、ねぎ、根菜類)を取り入れることが推奨されます
ということで治療院では柿と秋刀魚を食べることにしました
寒露は、二十四節気の1つで、通常10月8日または10月9日に訪れます。2025年は10月8日です
この時期は秋が深まり、朝晩の冷え込みが強くなり、露が冷たく感じられることから「寒露」と呼ばれます
暦の計算に基づき、太陽の黄経が195度に達する日であり、気候的には秋の清涼な空気と収穫の時期を象徴します
《寒露の特徴》
夏の暑さが和らぎ、秋らしい涼しさが増す時期。朝露が冷たく感じられ、紅葉が始まる地域も多いです
秋の虫の声が響き、渡り鳥が姿を見せ始めます。農作物は収穫のピークを迎えます。
日本では、古くから農業や自然と密接に関わる節気として意識され、季節の変わり目を大切にする風習があります
《寒露に関連する食べ物》
寒露の時期は秋の食材が豊富で、旬の食材を使った料理が楽しめます。以下は寒露におすすめの食べ物や食材です
《秋の味覚》
〈サンマ〉
秋の代表的な魚。脂がのったサンマの塩焼きは、寒露の時期に特に美味
〈栗〉
栗ご飯や栗の甘露煮など、ほっくりとした甘みが秋の食卓を彩ります
《きのこ〉
しいたけ、しめじ、舞茸などを使った鍋や炊き込みご飯が季節感を演出
〈サツマイモ〉
焼き芋やスイートポテトなど、甘みが増す秋の定番
〈柿〉
甘柿や渋柿を使ったデザートやサラダがおすすめ。
《収穫祭の料理》
寒露は収穫の時期と重なるため、新米を使ったおにぎりや炊き込みご飯が食卓に並びます
地域によっては、収穫を祝う行事で五穀豊穣を祈る料理(赤飯やお団子)も
朝晩の冷え込みに対応し、根菜や豆類を使った味噌汁や鍋料理が体を温めます
里芋やごぼう、かぼちゃを使った煮物やスープ
《寒露の食文化と風習》
日本では「旬」の食材を大切にする文化があり、寒露の時期は秋の恵みを活かしたシンプルな料理が好まれます
一部の地域では、収穫感謝の祭りや秋祭りが行われ、地元の食材を使った料理が振る舞われることも
健康への配慮: 冷え込む時期なので、身体を温める食材(生姜、ねぎ、根菜類)を取り入れることが推奨されます
ということで治療院では柿と秋刀魚を食べることにしました